4年間の学びを通して広がり、深まった「病を治す」夢。
叶えたいのは「誰もが生活の質を維持できる社会」。
川村祐貴
2017年入学 第1期生
イエール大学
サンモール・インターナショナル・スクール出身

循環器疾患に対する医療に携わることを目標に定めている川村祐貴さん。医療者としての将来を見据えた彼が進学先として選んだのは、伝統的なリベラルアーツ教育の精神が根付くイェール大学でした。

循環器疾患に対する医療に携わることを目標に定めている川村祐貴さん。医療者としての将来を見据えた彼が進学先として選んだのは、伝統的なリベラルアーツ教育の精神が根付くイェール大学でした。 4年間の学びを経て、2021年現在に卒業を迎えた川村さんに、“イェール大学で得たもの”について伺いました。
4年間の学びを経て、2021年現在に卒業を迎えた川村さんに、“イェール大学で得たもの”について伺いました。
August, 2021
古典を大切にするイェール大学で、
“理(ことわり)”を追求したい。
― 川村さんは幼い頃から、医師として循環器疾患に向き合うことを決めていたと伺っています。循環器疾患という分野まで定めているのに驚いたのですが、どんな経験や思いを経て、この具体的な目標を持つようになったのでしょうか?
小学生の頃に、祖母が動脈瘤で倒れてそのまま命を落としてしまいました。その時に感じた、昨日まで元気だった人があっという間に亡くなってしまう衝撃と、病院でこんな装置に繋いでも何もできないんだっていう悔しさがきっかけです。自分だったら何とかしたい、と。でも同時に、これまでと同じようなことをやっても救えないんじゃないかということも感じました。いろいろ考えていく中で、ちょうどその当時、iPhoneが初めて登場して、理数系の力というか、新しいテクノロジーが世界を変えていく様に感銘を受けたこともあって、今までみんながやってこなかった方向から循環器疾患を考えたら、上手くいくんじゃないかと考えたんです。もともと私が数学をある程度好きだったというのもあるんですが、医学は伝統的に生物学で、数学を好きな人はあまり多くない分野なので、それをもっと、自分がその境界を広げていけば、命を救う新しい方法が見つかるんじゃないかと思いました。
― 医師になること、循環器疾患から命を救うこと、そのための新しい方法を見つけること、という、かなり具体的な目的がある中で、イェール大学を進学先に選んだ理由は何でしょう?日本やイギリスの大学など、学部1年生から専門的な学びに入る場所の方が近道のように思えてしまうのですが…。
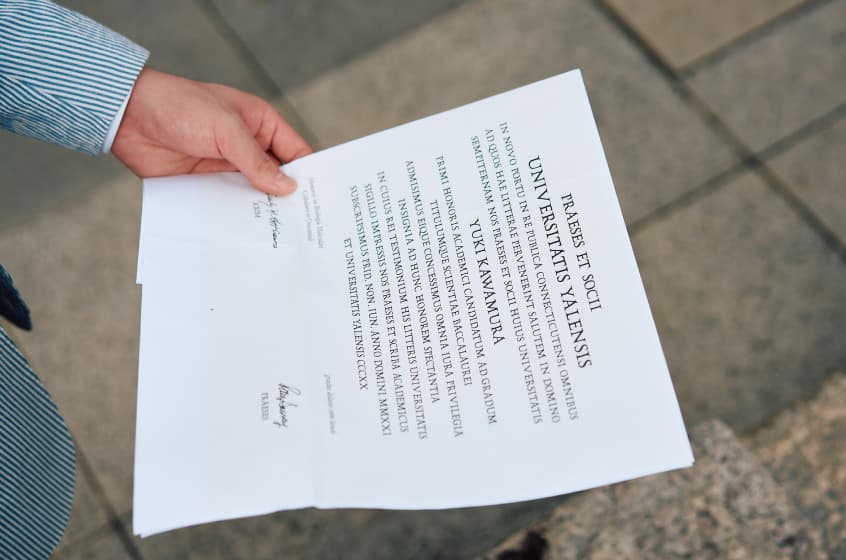
イェール大学の卒業証書(コピー)。ラテン語で書かれている。
イェール大学は、リベラルアーツカレッジと研究型大学の融合と言われていて、学部教育という点ではリベラルアーツ教育を大事にするものの、環境としては大規模な研究が行われる研究施設も整っている大学なんです。日本でもアメリカでも、医学部が独立して離れたキャンパスにあることが多いと思うのですが、イェール大学の医学部は寮や図書館、他の学部と同じキャンパス内にあります。他の学部生との交流もできますし、必然的に学問に打ち込める環境なのが、選んだ理由の1つですね。なぜ学部教育でリベラルアーツを選んだかというと、医学って、ものの理を追求するものだと思っているので、それをもっと理解した上で、次に進みたいと考えたからです。例えば1つ、イェール大学の特徴で面白いエピソードを聞いたことがあるんですけれども、法学部の試験で税について問う時に、他の有名大学では税制の細かい知識を学生に問うところを、イェール大学では、一問目が「税金は必要か」だったらしいんです。そもそも税金って必要なのか、なぜ税金を払うのかっていうところを突き詰めるような感覚にすごく惹かれました。カリキュラムもすごく伝統的というか、1年次の学生の多くがプラトンやアリストテレスを読んで、そこから人間性を見つめ直していくというような、古典を大事にする環境がいいなと思いましたね。また、校風に公共福祉、社会奉仕という考えが根付いているのも、イェール大学を選んだ理由の1つです。例えば、イェールのビジネススクールに通う学生は卒業後、NGO団体や政府機関に進む人たちが多いと言われています。あらゆる物事の考え方において、社会に対する貢献というのが根底にあるというのが、医学を志す者としては魅力的だなと感じました。

専攻分野だけにとらわれず、様々な“知”に触れる4年間を過ごした川村さん。
大学教育を受ける意義は“批判的思考”にある。
― 4年間の学部教育を通して、プラトン、アリストテレスなどの古典哲学の他にも、文学、社会科学の授業も受けられたと聞いています。これらの学問は、将来、医師を目指す川村さんにどのような視点、考え方を与えてくれたと思われますか?
1つは、“関連性を見出す面白さ”。Aという問題を見ている時に、違う角度からの視点を結びつける力って、仕事でも研究でも大事だと思うんです。リベラルアーツ教育を通して、一見、全く違うことの関連性を見出して、それを活かす楽しさを知った気がしますね。もう1つは、 “批判的思考”だと思います。あらゆる物事に対応できる、考える指針ができたというか。細かく習ったテスト範囲って絶対いつか忘れると思うんですけど(笑)、忘れた時にどうやって情報を取り入れるか、情報を批判的に読み取って、取捨選択して、自分のものにするのかっていうのを、包括的に学んだと思います。知識っていうのはある程度あった方がいいとは思うものの、そんなに必要はないと思うんです。ある経済学者が経済的な理論を全部言えるからすごいかというと、そういうわけではないと思うし。どんどん情報が手に入りやすくなっている今の時代になぜ大学教育を受けるのか、大学教育を受けた人と受けていない人でどこが違うべきかと言ったら、“批判的思考”だと思います。これってどのぐらい信頼性があるのかなとか、このエビデンスを見てこの決断にちゃんと達するのかなというふうに考える人たちが、大学教育を受けた人だと思うんですね。大きな問題が与えられた時に、自分だったらどうアプローチするかというのを、論理立てて、起承転結のある考え方を持って取り組むことができる。4年の間に、この力をすごく仕込まれたと思っています。
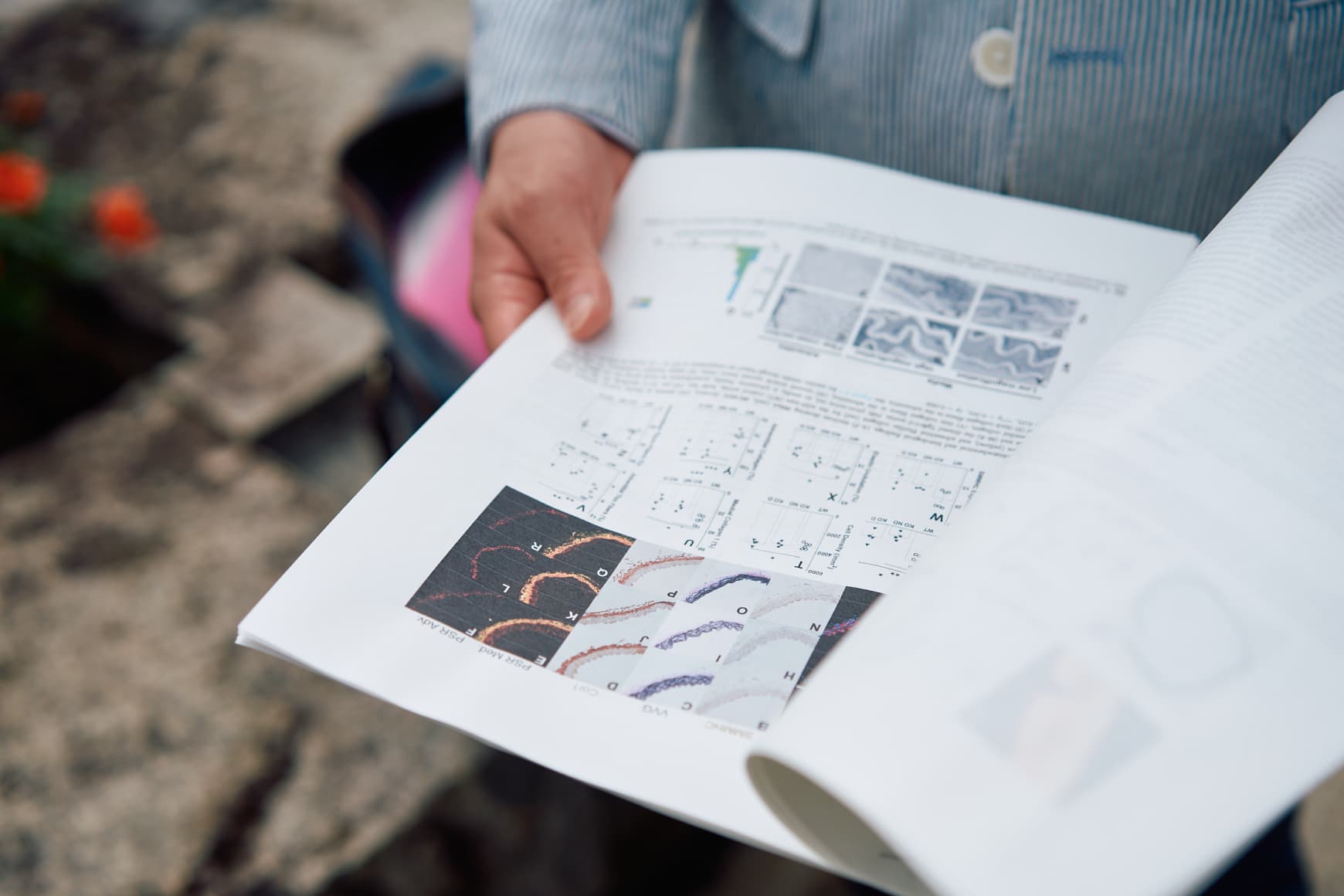
研究を元に執筆した論文。「イェールに入る時は生物学の知識がありませんでしたが、手厚い指導のおかげで研究を行うまでになりました」
― “批判的思考”、“考える指針”を得たことで、入学当初から持っていた目標、循環器疾患、特に動脈瘤に対する医療について、何か考えに変化はありましたか?
イギリス渡航前に、川村さんの地元でお話を伺った。
最初は、「血管の病気なんだから、まずそれを治そう」っていう限定的な発想だったんです。それこそ小さい頃は、薬を作って、「これを飲んだらもう絶対に治りますよ」って言ってあげることが夢でした。手術をすることもなく治療できる方法があればいいなって思っていたんですけれども、人間の体ってそんなシンプルでもなく…。そもそも、なぜ動脈瘤は死に至ることが多いのかをよく考えた時に、発見が遅れることが多いから、重症になってしまうとなす術があまりないから、つまり、早期発見、早期治療が必要になるんですけど、みんながみんな人間ドックに行って検査をすればいいかというと、そういうことでもなくて。例えば、何人も子どもがいて、家の大黒柱で、仕事を休んで病院に行くという悠長なことを言ってられない人こそ、病気になったら一番大変なのに、そういう人に対して、高度で高額な検査をいっぱいすればいいっていうのは絶対に違いますよね。でも複雑な検査をしないと見つからない病気なので、そこにすごい憤りを感じて…。政治哲学者ジョン・ロールズは「最も不遇な状況におかれた人々の暮らしを改善できる社会にこそ社会正義が宿る」と述べています。最先端の高度な医療で一部の人しか助けられないのではなく、もっと簡単で、最小限の負担で、かつ安くできるようなことを考えていかないと、一般的にこの夢を実現することはできないんじゃないかって思うようになりました。
目標は毎日の小さな幸せを支える、
裏方に徹した医療。
― 経済的な格差など、個人を取り巻く環境や社会のことにも目を向けるようになったということでしょうか。

そうですね。プラトンが「国家」という本の中で、リーダーシップを育成するためにはさまざまな分野の内容をゆっくり学んでいくことが必要だと言っていますが、医者としても、例えば経済だとか、他の公衆衛生のことも考えて、全体を俯瞰して答えを出さなきゃいけない場面が必ずあると思うんです。ただ手術が上手いとか、人体に関する知識が豊富だというだけでは足りないと思うんですよね。だから、「循環器疾患を治療できるようにする」よりも、「最小限の負担で循環器疾患を治療できるようにする、循環器疾患による突然死や後遺症を防ぎ、誰もが生活の質を維持できる社会を実現する」に、将来の目的もちょっと広がりました。この世の中から病気を全てなくすことはできないにしても、日々の楽しみを病気によって邪魔されることはなくしたいなと思っています。家族とご飯を食べるとか、子どもの成長を見るとか、毎日の小さい幸せを裏方で支えるような、裏方に徹した医療をやっていきたいです。
― 今年2021年秋から、イギリス、ケンブリッジ大学に進学予定と伺っています。アメリカではなく、イギリスの大学院にされた理由は何でしょうか。また、ケンブリッジ大学の、その先、も考えていたりしますか?
イギリスの臨床は「病気じゃなくて、人を診る」という教育をしてくれるっていう話をよく耳にすることがあって、それで、自分の思うことに通ずるところが多いなと。行きたいなと思ったというのが理由の1つですね。もう1つは、伝統的な大学だというところ。これ、理由としては全然関係ないっていう人もいるかもしれないんですけど(笑)。ニュートンが万有引力の法則を発見したのはケンブリッジですし、血液が体内を循環するっていうのをウィリアム・ハーヴィが発見したのもケンブリッジ。先人がすごいものを築き上げた環境の中で学ぶっていうのは本当に感動的で、自分のモチベーションにもなるんですよ。ケンブリッジ大学を卒業したら、独立して、研究室を持って、医学をどんどん推し進めることをしていきたいです。現役を退いた後は、私が学んだ教育を日本に持ち帰ってきて、人を育成するようなことができたらなと思っています。先生が言ったからこうだとか、教科書に載っているからこうなんだとかではなくて、批判的思考ができる人材を育てられたらいいなと思いますね。
College Life
― 最後に、海外進学を考えている中高生のみなさんにアドバイスをお願いします。
特にアメリカのトップ大学って、資金もリソースもあるので、五つ星ホテルに泊まるみたいだっていう話を私はよくするんです。受動的にならないことはすごく大事だと思っていて、一生泊まれないようなホテルに宿泊するって思った時に、その機会を余すことなく全部使い切りたいじゃないですか。いろんなボタンを全部押してみるとか(笑)。その感覚と同じで、大学にはいくら使っても使いきれないくらいのリソースがあるんですよ。ある意味、4年間っていう制限付きのバイキングみたいな感じなんだから、座ってコーヒーをすすってるだけじゃなくて、どんどん自分から行って、お腹いっぱいになるまで食べようよっていうのが私のメッセージですね。とことん使い切って、得られるものは全部得た、それで自分の身になった、って言えるようになって卒業してほしいと思います。

川村祐貴 2017年入学 第1期生
イエール大学
サンモール・インターナショナル・スクール出身
2021年にアメリカ・イェール大学を卒業、イギリス・ケンブリッジ大学医学部へ進学。イェール大学在学中には、自身が筆頭著者を務める循環器疾患の研究論文を発表。座右の銘は「徳においては純真に。義務においては堅実に」。
