多角的な視点を持った “ものづくり” で、
多様な人が生きる世界にインパクトを与えたい。
池田楓香
2022年入学 第6期生
ブラウン大学
広島女学院高等学校出身
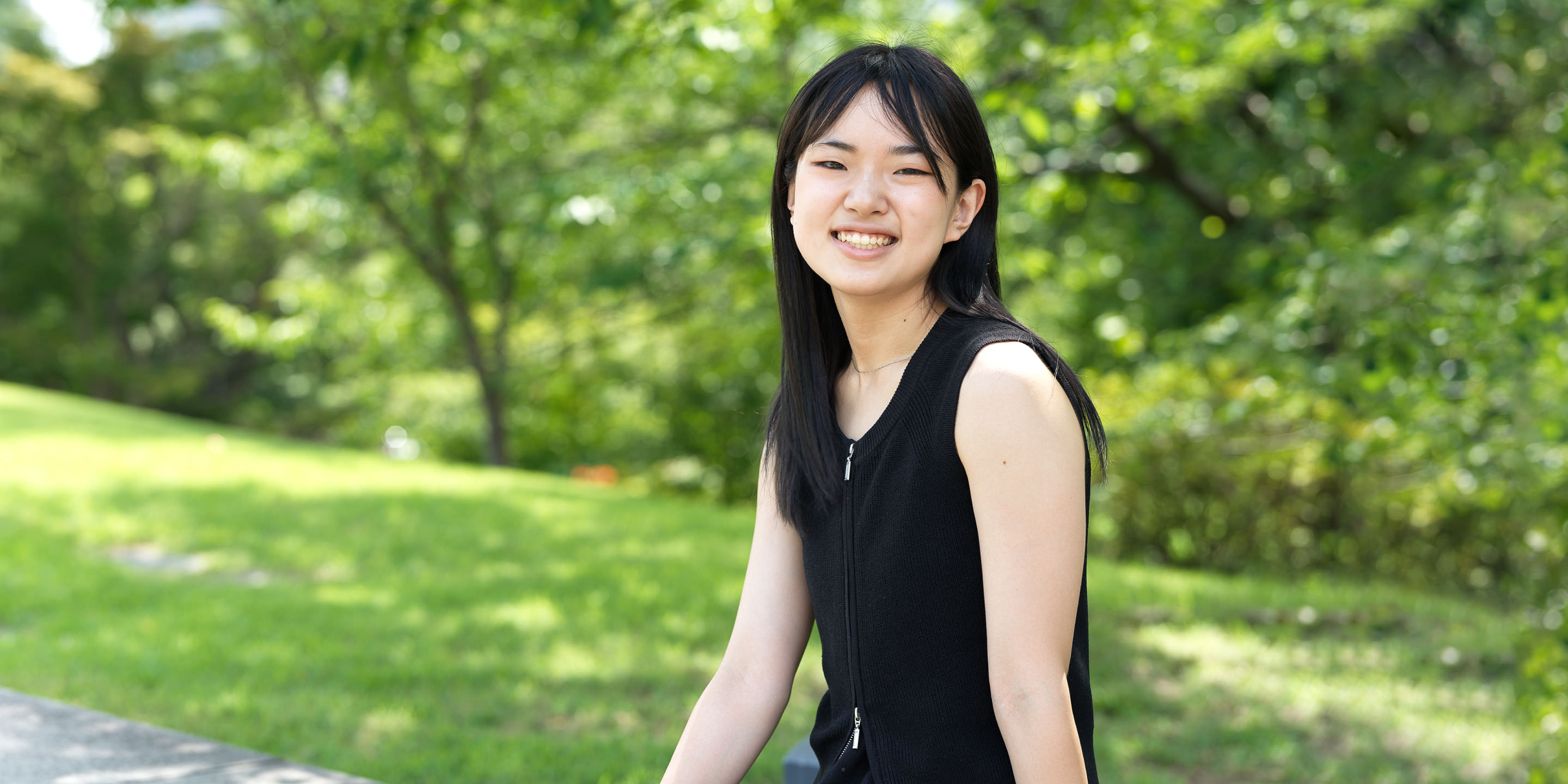
アメリカ·ブラウン大学で、コンピューターサイエンスとデザイン工学をダブルメジャーとして学ぶ池田楓香さん。

アメリカ·ブラウン大学で、コンピューターサイエンスとデザイン工学をダブルメジャーとして学ぶ池田楓香さん。幼い頃から持ち続けた “ものづくり” への情熱が、どのような過程を経て池田さんをブラウン大学へ導いたのか、ブラウン大学にいる今、将来はどんな道を考えているのか、お話を伺いました。
幼い頃から持ち続けた “ものづくり” への情熱が、どのような過程を経て池田さんをブラウン大学へ導いたのか、ブラウン大学にいる今、将来はどんな道を考えているのか、お話を伺いました。
August, 2024
“ものづくりの光と影” を知ったからこそ、
世界をよりよく変えるものを作りたい
― 高校3年生当時から、将来は「ものづくりを通して環境を変えたい。エンジニアリングで、実際に人が触れる機器でインパクトを与えたい」という夢を掲げておられました。世の中を変える方法として面白いアプローチだなと思いますが、どのようなきっかけがあって、この目標を思い描くようになったのでしょうか。
もともと、子どもの頃から何かを作ることが好きでした。「つくってあそぼ」という工作番組を録画するほど大好きで、それを見ながらいろいろ作ったり、レゴを組み立てて遊んだり。幼い頃の私にとって、ものづくり=楽しいこと。でも小学6年生の時に広島に引っ越し戦争の歴史を学ぶなかで、原子爆弾は極端な例かもしれませんが、ものを作ることに伴うリスクに初めて意識が向くようになり、ものづくりがなんだか急に怖く感じるようになって……。それから高校生の中盤まで、核の歴史を伝える活動や平和のための署名活動の方により力を入れるようになりました。
転機になったのは高校2年生の頃。「学校が面白くない」と落ち込んでいた10歳年下の妹のために、知育のおもちゃを自作したんです。作ったのは全面をホワイトボードにした積み木のブロックを拡張したようなおもちゃ。組み立てた後にペンで好きなものを描き込めるので、使い方や組み合わせ次第で楽しみ方が無限にあります。それを妹が喜んでくれたのが、私もすごく嬉しくて。何かを作ることで人を楽しませたり、救うことができたりするんだと、その時ものづくりのパワーみたいなものを思い出し、やっぱり私は将来ものづくりに携わりたいと決めました。


持参してきてくれたのは、多関節の歩行ロボット。大学にある3Dプリンターでパーツを作り装着するなど、自分で改造している。
とはいえ、ものづくりに伴うリスクを無視することはできません。それなら、リスクもきちんと考慮した上でものを作れる人になりたい。高校3年生当時は人の生活に関わりのある機器を作るという漠然としたイメージを抱いていましたが、今はロボットを作る技術者になることを目指しています。自分の作ったロボットで世界に良いインパクトを与えることができればと考えています。
ものづくりに「これしかない」は存在しない
多様な人、ニーズに応える作り手になるための
学びを求め、アメリカへ
― 将来の目標が見えたところで、エンジニアリングを通したものづくりを学ぶ場として海外の大学を、なかでもアメリカのブラウン大学に目を向けたのはなぜですか?
まず、海外大への進学を考えるようになったのは、いろんなバックグラウンドを持つ人たちがいる環境に身を置いて、多様性のある学びをしたいと思ったからです。私は小学生の頃、アメリカの各地とアイルランドで過ごした経験がありますが、国や地域によって考え方がかなり違うことに驚いた記憶があります。例えば、第二次世界大戦についてだと、アメリカでは真珠湾攻撃をはじめ、加害者としての日本の姿が語られますが、日本では広島·長崎への原爆投下による被害に目がいきますし、一方でアイルランドは第二次世界大戦にあまり関わりがなかったので、より焦点が当たるのは国内の飢餓の歴史。地域ごとに注目する観点が違うと、おのずと注目する課題や対応の仕方に差が出るんです。

「ものづくりをする人と、作られたものを受け取る側には、まだ大きな隔たりがあると思います」と話す池田さん。
こういった違いは、ものに対する見方にも出てくると思っています。例えばドローンって、アメリカではカッコいい撮影道具という扱いですが、戦争が起きている地域に住む人たちからすると兵器の一種で、人を傷つけるために作られているものという認識が強いはず。つまり、自分がベストだと思うプロダクトが、必ずしも他の人にとってはそうではないというか、ものづくりにおいて「これしかない」って、ないんですよね。そう考えると、自分の視点や経験だけでは不十分で、ユーザーが本当に望んでいるもの、使う人にとって最適なものを多角的に捉えられるような、自分の中に多様性がある人になりたいです。
3年次、4年次と楽しみにしているのは「卒論を書くこと」。今の時点ではロボットの素材や色が人間に与える影響を研究したいと考えている。
コンピューターサイエンス×デザイン工学、
時々ダンスパフォーマンス
学問の化学反応が楽しい!
自分の多様性を育てるための学びができる、そんな環境を求めた時にブラウン大学に魅力を感じたのは、幅広い学びを大切にするアメリカの大学のなかでもさらに自由があるところ。私は工学部に行きたいと思っていたのですが、工学部と他の学部がきっちり分かれている大学が多い一方で、ブラウン大学は学部に関係なく全ての学部の授業を受けることができます。実際、今の私の専攻はコンピューターサイエンスとデザイン工学です。工学部のみだとロボットのハードウェアを作れるけれどコードは書けなかったり、反対にコンピューターサイエンスだけでは何かを組み立てたり、回路を作るということができないので、私にはダブルメジャーしかないじゃんって気づいて、やってみることになりました。授業のスケジュールはキツキツなんですが(笑)、頑張っています。
入学してからの2年間、いろんな講義を受けてきましたが、一番印象に残っているのが「TAPS(Theatre Arts and Performance Studies)」という授業。仲の良い教授に「もっと変な授業も受けてみなよ。ダンスとかパフォーマンス系の授業とかどうなの?」と言われて参加してみたんです。振付師として初のテニュア(無期雇用教員)となった元バレエダンサーの教授が教えてくれたのですが、「振付とロボット、AIの関係性」というテーマの講義が本当に面白くて。ロボットらしい動きは何なのか、ロボットを身体と見立てた場合にその動きをどう捉えるのか、音楽や映画が私たちのロボットに対する印象·指向にどんな影響を及ぼしたのかなど、今までの私にはない視点でロボットを考えることができて、新しい発見が多くありました。

2年次が終わり、受講スケジュールは自分の好きな講義ばかりに。「どんなに忙しくても、好きなことだから集中して頑張れます」
あと、「Medical Anthropology」という授業は、財団生で同じブラウン大学に通っていた先輩の石山咲さんに勧められて受講したもの。授業のことだけでなく、それこそ大学生活が始まる前に「寮にはどういう荷物を持っていけばいいですか」、「日本から絶対持っていった方がいいものって何ですか」など、先輩方に聞いてアドバイスをもらっていました。先輩後輩、同期との関係性が結構強いのが、この財団の魅力かなと思っています。特に私と同じように地方の高校出身で、周りに海外大を目指す人が誰もいなかったり、アドバイスをもらえるような人と知り合う機会がなかったりする場合は、財団のコミュニティのおかげでコネクションが広がって、いろんな人たちと出会えるのは本当に楽しいですし、貴重な繋がりです。みんなそれぞれに興味分野が違うので、「国際政治は今、この話題が面白くて」とか、「古代エジプトのこういうテーマで勉強していて」とか、話を聞くだけで世界がすごく広がる感じがあります。
― 財団のコミュニティの雰囲気はどんな感じなのでしょう?
ざっくり言うと、みんなとにかくいい人。実は私、財団に所属する前はとにかく怖かったんですよ。奨学金を受給する人たちはみんな、数学オリンピックとか国際会議に出ているようなすごい人たちというイメージを持っていたので、私はそんな人たちの中でやっていけるのか、仲良くできないんじゃないか、とすごく恐怖を覚えた記憶があります。でも実際会ってみると、みんな良い意味で普通(笑)。自分と同じようなことで悩んでいたり、葛藤したりしていて。学びたいことや将来の夢に対して、すごくパッションを持った、普通の大学生なんだなって知ったのは、すごく救いになりました。
College Life
目的地がはっきりあるなら、
そこまでの道のりはどれを選んでもいい
― ブラウン大学で2年間を過ごした今、池田さん自身はどう変化したと思われますか?
良くも悪くも、自分の掲げているビジョンを達成する道は多くあるんだなっていうことを発見しました。人間と科学技術、テクノロジーが安全に共存できる社会を作りたいと思っているけれど、そのための方法は研究を通してもできるし、または民間の会社に所属してロボットを作ることでも叶えられるし、起業する方法もあります。「ドラえもん」のエピソードの一つで、「未来が分かった上でいろいろ行動したら、未来が変わって大変じゃないか」と言うのび太に対して、ドラえもんが「例えば、東京から大阪に行く方法はバスでもいいし、徒歩でも車でも、新幹線でも行ける。手段を変えても目的地は同じだから大丈夫だよ」って励ましていた場面がすごく印象に残っているんですけど、まさにそうだなっていうのを感じています。私がどういう道を通っても、自分の達成したいものは達成できるはず。良くも悪くもいろんな道を発見する日々です。
柳井理事長との面接でも話をしたことで、今も変わってない私の考え方に、「Planned Happenstance Theory」、計画的偶発性理論、というものがあります。人生の8割は偶然の出来事において構成されるという理論です。どんなに計画しても人生の8割は偶発性なら、その時の発見や出会いを大切にして思わぬ人生になっていく方が私はワクワクします。なので、今は大学での一日一日を精一杯楽しみたいです。
― 最後に、海外進学を迷っている中高生のみなさんにメッセージをお願いします。

「卒業後は大学院に進むのか、就職するのか決めていないけれど、ものづくりには携わっていきたいです。そしていつか、自分の作ったロボットで世界を変えたい」
一番伝えたいのは、勇気を持って自分の世界を広げてみてほしいということ。これは、自分の興味がある分野においての知識を深める手段としても有益である一方で、「自分の今いる社会だけが全てじゃない」ということを知るのは、個人としてもすごく支えになる価値観だと思っています。例えば、地元だけが自分の世界だと、ちょっと嫌なことがあると一気に息苦しくなるかもしれないけれど、世界まで視野を広げられれば、一気に生きやすくなります。一歩の勇気が一生の宝物になると思うので、ぜひ勇気を持ってチャレンジしてみてください。
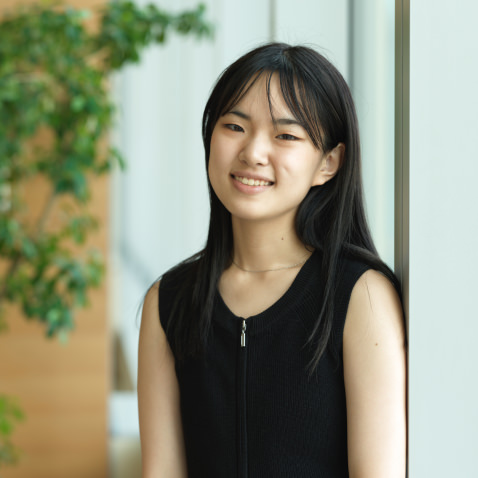
池田楓香 2022年入学 第6期生
ブラウン大学
広島女学院高等学校出身
大学では、「Brown Band」(マーチングバンドのような部活)、「Design For America」(ものづくりで社会問題にアプローチする方法を模索する部活)、デザイン部の設立など、課外活動も精力的に行う。3、4年次で楽しみにしていることは卒論。ロボットの素材や色が人間に与える影響について研究する予定。
